|
『ロスト・ソウルズ』ポピー・Z・ブライト |
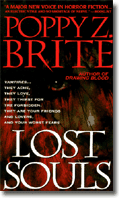 (ポピー・Z・ブライト著/Abyss ) |
|
●作者紹介 ポピー・Z・ブライトPoppy Z. Brite。 |
●作品紹介 『ロスト ソウルズ』 翻訳版:柿沼瑛子訳/角川ホラー文庫 ここは僕のいるべき場所ではない。15年間いつも独りぼっちで、自分の本来いるべき場所を求め続けてきた。「両親のふりを演じ続ける善意の愚か者たち」養父母は僕をジェイソンと呼ぶけれど・・・ある日見つけたメモ。捨て子だった僕のほんとうの名前は「ナッシング(何者でもない)」。  パンク・バンド「ロスト・ソウルズ?」に心ひかれ、ナッシングはメンバーが住むミッシング・マイルを目指して家を出る。だがヒッチハイクの道中で出会った緑の瞳の酷薄な青年ジラー。ジラーは少年に「血」の味を教える――やがて明かされる恐るべき真実。ナッシングはヴァンパイア(吸血鬼)であるジラーと彼に魅せられた人間の少女を両親とし、ヴァンパイヤの宿命として母親の肉体を喰い破って生まれてきたのだった。ナッシングはジラーとともにほんとうの故郷、ニューオリンズに戻ってゆく。 パンク・バンド「ロスト・ソウルズ?」に心ひかれ、ナッシングはメンバーが住むミッシング・マイルを目指して家を出る。だがヒッチハイクの道中で出会った緑の瞳の酷薄な青年ジラー。ジラーは少年に「血」の味を教える――やがて明かされる恐るべき真実。ナッシングはヴァンパイア(吸血鬼)であるジラーと彼に魅せられた人間の少女を両親とし、ヴァンパイヤの宿命として母親の肉体を喰い破って生まれてきたのだった。ナッシングはジラーとともにほんとうの故郷、ニューオリンズに戻ってゆく。
「ロスト・ソウルズ?」のボーカリストである「ゴースト」は、未来を予知し人の心を読む、祖母ゆずりの神秘能力をもつ。その能力ゆえに孤立する彼が唯一心をゆるすのは幼なじみでギタリストのスティーブ。ナッシングを核に彼らとジラーの運命が交錯する。スティーブの恋人アンはジラーと関係を持ち、みごもった彼女はジラーを追って出奔。そして彼女を捜しに、スティーブとゴーストはニューオリンズにやってきた。 ロックとドラッグに酔いしれる現代の吸血鬼をテーマにニューオリンズの闇を描く。耽美ホラーと銘うたれるが、肉体の境界をこえて愛と癒しを求める魂の物語である。 |
| アメリカ南部を流れる「血」の味 保守派プロテスタント勢力の強い、バイブル・ベルトと呼ばれるアメリカ深南部にありながら、ニューオリンズはどこか異教的な退廃の匂いがする魅力にあふれる街ということになっている。時が止まったような優雅で古めかしい街並みをアンを探してさまよいながら、ゴーストは「『エンジェル・ハート』に出てくるような私立探偵を雇うべきだった」とつぶやく。その映画「エンジェル・ハート」でも、大鍋で煮えたぎっているガンボと、そこに顔を押しこまれ、煮え爛れた男の死体が印象深いシーンをつくっていた。どこかブードゥーの魔女がかきまぜる鍋のような、赤やら緑やらどろどろとした得体のしれないごった煮というイメージを抱かせなくもない不可思議な料理。いったいどんな味がするのだろうか。  スティーブとゴーストは、ニューオリンズにやってきてまず最初にガンボを食べる。吸血鬼の子をみごもって失踪したアンの身の上への不安や、傲慢で残酷な吸血鬼ジラーへの怒りで、ニューオリンズに着くまで食事も喉にとおらなかったらしいスティーブだが、ガンボはそのおいしさに3杯もお代わりせずにはいられなかった。一方、どうやらゴーストは自然食主義者か菜食主義者らしく、日頃はスティーブにも「もやしや豆腐」ばかり食べさせようとしているらしいが、ガンボのボウルを前にすると、そのたちのぼる湯気さえ逃さないように吸いこみ、「瞼を喜びにふるわせ」ながら夢中になって味わう。 ガンボのおいしさは、口に含んだときに「たっぷり身が入ったエビとカニのうまみ、フィレパウダー(サッサフラスの葉)のつんと刺激的な香り、オクラの柔らかい口当たり」など、いろいろな要素が舌の上で溶け合うことで生まれるようだ。 ガンボの鍋には、200年にわたってニューオリンズを構成してきた人々の要素が入り混じり、溶け合ってその複雑な味を生み出している。先住民族のチョクト族、フランスとスペイン、アングロ=サクソン、アフリカン、それぞれが対立し、ときに融和することで醸しだされる何ものでもない何か。それに触発されてルイジアナでは独自の料理文化が発達してきた。その代表格のガンボはこの土地の歴史がとけこんだ、この土地の「血筋」を象徴するようなスープである。これを食べるのはニューオリンズに来たという証左、この街そのものを味わうようなものなのだ。 新鮮な素材をふんだんに使った熱々のガンボを口に含むと「命の鼓動そのものと共に口中に流れ込んでくる熱い豊潤な味」を感じる。これは小説中に繰り返される主題ともいえるある味覚の表現だが、ガンボの味わいにはとてもしっくりなじむようなのだ。ほんとうはヴァンパイヤたちが糧とするものについての形容であるのだけれども……。 |

|
| 小阪ひろみ |